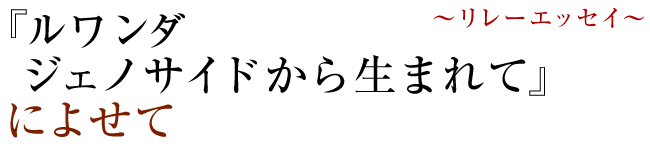
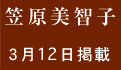

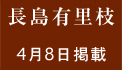
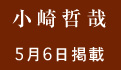
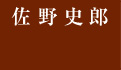
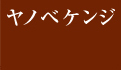
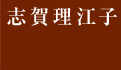

追記〜本文の前に〜 2011年3月16日
私はこの原稿を、3月6日に姫野さんに届けた。その直後の3月11日に今回の大震災が起こった。
言葉を失いつつ、言葉が溢れる。すでに始まっている長い闘いに向けて、伝えたい言葉がある。だから、以下の「『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』に寄せて」に追記したい。
産まれることも死ぬことも産むことも、人智を越えた自然の営みだと思う。問題は、それを誰がコントロールするのか/されるのかということだ。死ぬこと自体が不幸なのではないと敢えて言いたい。どのように死ぬのかが問題なのだと思う。
また、「健康である」ということは、とても社会的なことだと思う。すべての人間は、健康を含めた「安全と安心」を保障される権利と必要性を持っている。
私は、災害も紛争も、「しわ寄せ」という構造がひとつの大きな問題だと思っている。情報が集中する地域からそうでない地域へ。大都会からそうでない地域へ。宗主国から植民地地域へ。「しわ寄せ」られている側の切実さに対して、「しわ寄せ」している側は常に無関心、または見当違いの同情を寄せるかである。
同情ではなく同苦へ。
今回、東日本大震災発生から5日目を迎えて、特に報道/ジャーナリズムについて多くの事を考えさせられている。「『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』に寄せて」の本文は、そのことと関連している。
* * * * *
ジョナサン・トーゴヴニク写真集
「ルワンダ ジェノサイドから生まれて」に寄せて
過去に起こったあらゆるジェノサイド(集団虐殺)を想像してみる。
人間が、かくも残虐/非道な行為を、与える側にも受ける側にもなり得るということ、また、人間がかくも淡々と強くなり得るということについて、私たちは出来るだけ若い時期に、出来れば両方を知っておくほうがいいと思う。
残虐/非道な行為はもちろん与える側にも受ける側にもならないのがいいに決まっている。しかしそれから逃れられないとしたら?逃れられない構造があるとしたら?その構造を変えるための、あるいはその構造の中でさえ生き抜くための強さと智恵と行動は、何から生まれるのだろうか。
無知と無関心、そして忘却は恥ずべきことだ。そして無知ゆえの無垢な純情さは、出来事の痕跡や証言に向き合うことを臆病にさせる。
私がナチスのホロコーストについて知ったのは中学生の頃だ。崇高な正義感などからでは全くなく、当時の貴重な証言を記した「アンネの日記」や「夜と霧--ドイツ強制収容所の体験記録」(旧版・写真図版入りの方)といった書籍を私に示した大人が居たからだ。
ナチスのホロコーストは大変に有名であったから、私は大人になってからもそれを覚えていて、第二次世界大戦に対するドイツと日本それぞれの市民の、そして自分自身の、現在の意識と行動について興味を維持することが出来ている。
数ヶ月前、49歳にして私は久しぶりに自分の無知を大きく恥じた。私がルワンダの集団虐殺・集団暴行について初めて知ったのは、数年前に観たNHKテレビのドキュメント番組によってだった。その番組を観た時には「組織化された殺戮」と「生き残り、生き続けるということ」について、何らかの強い印象を受けた記憶がある。しかしここ数年間、私はその集団虐殺が起こったルワンダという国がどこにあり、それはどのくらいの規模で、そして何が原因で起こったのか、詳しく知ろうとはしなかった。その番組には情報が含まれていたのかもしれないが、数年経った今は忘れてしまっていた。
そして2010年12月、私は京都造形芸術大学で開催された「時代の精神展」第一回としての「ジョナサン・トーゴヴニク写真展/ルワンダ ジェノサイドから生まれて」を見る機会に恵まれた。私は被写体となった女性達の証言内容を知ると同時に、写真家の動機と意思に興味を持った。それで、この展覧会と同写真家による写真集「ルワンダ ジェノサイドから生まれて」の企画者である竹内万里子さんの助言を得て、いくつかの資料を読んだり映像作品を見たりした。
そこから知り得て一番愕然とした事は、100年前の植民地政策を始めとした欧米諸国の行為が、ルワンダを含むアフリカ諸国の今も続く苦しみの原因として大きな影響を及ぼしていること、特にルワンダにおける「民族の対立」を生んだのは主にベルギーの植民地政策によるものだったこと、そして今も続く長期・広域・大量に及ぶ紛争・虐殺・レイプ・貧困・難民問題に対して、国連や欧米社会の示す関心は、白人における同様の問題に比べて明らかに低い、いや、むしろ非道に見放している、ということであった。日本で生活する私は、その欧米社会が主に提供する情報によって世界を意識していたにすぎなかった。この私の無知は愚かであり残酷ですらある。
ここで私は、「自分が今書いた言葉」の、薄情さと野蛮さに立ちすくみそうになる。私は安全な場所でのんきに自らの無知と怠惰を発表している。おめでたいことだ。
しかし私は今、知らなかったことを知っている。それは、それらを知る前と後とでは、文字通り世界の見え方が変わるような事柄である。2冊の本といくつかの映画とインタビュー記録は、立ちすくんだ私が新たに踏み出す方向を示してくれた。
「ルワンダ ジェノサイドから生まれて」の写真家ジョナサン・トーゴヴニクはインタビューの中で、ジェノサイドの際のレイプから子どもを産んだ女性たち対して「もし手立てがあるとしたら、自分の子どもたちの将来をどう考えますか?」と質問したと話す。すると彼女たちは「教育だ」と答えたというのだ。これは何を意味するのか?報復や金や権力が必要だと思う時もあるかもしれない。しかし彼女たちは全員が「教育だ」と言ったのだ。ひとりで生きる能力を身に付けるために。自分たち母親はそんなに生きられないでしょうからと言った、という。
映画「ルワンダの涙」のプロデューサーであり、BBCジャーナリストでもあるデビッド・ベルトンはインタビューでこう言っている。「私にはルワンダの人々の代弁者にはなれない。私に語れるのは自分が経験したことだけだ。この映画は欧米人の立場から『私たちはこうやってあなたたちを見捨てたのです』という内容だ。これを見ることによって、ルワンダの人々のこの事件に対する見方が変わるかもしれない。」この映画はルワンダで撮影され、事件の当事者であるルワンダ人と一緒に製作された。それは当事者へのエンパワメントであり、その思想はほとんどドキュメンタリーのようであるが、しかし多くの人が見やすい劇場映画として仕上げるという意思に貫かれている。
そして「ジェノサイドの丘」の著者、フィリップ・ゴーレイヴィッチ。この驚異的なルポルタージュは、どのように人はこの世界を想像するのか、その想像という闘いのプロセスを人に伝えることの可能性と責任の在処を、痛みを伴う希望とともに私に取り戻させてくれた。
* * * * *
写真家ジョナサン・トーゴヴニクはインタビューの中で次のようにも言っている。「あらゆるフォトジャーナリストはアクティビスト(活動家)だと僕は思います。」私はこの意見に賛成だし、ジャーナリストとアーティストはこの点において似ているとも思う。そして、ジャーナリズムも写真や映画のような芸術表現も、どちらも受け手の反応があって初めて成立する。
ルワンダに続くスーダン等々での紛争。そして、今夜もインターネットが報じるリビアでの無差別虐殺。その状況は、17年前に起きた事件を描いた映画「ルワンダの涙」や「ホテル・ルワンダ」が伝えるものと呆れるほど酷似している。現地からの声なき声と、欧米社会(日本もそれに含まれる)の対応の、絶望的なギャップという点で。
しかし同時に、その「声なき声」を伝播させることが可能だということを、私たちはすでに知ってもいるのだ。
2011年3月
ブブ・ド・ラ・マドレーヌ
* * * * *
資料情報
「ジョナサン・トーゴヴニク氏のインタビュー」
http://www.mediastorm.com/publication/intended-consequences
(本文中の引用は、竹内万里子氏の翻訳による。)
「ルワンダの涙」2005年、イギリス・ドイツ合作、DVD
「ホテル・ルワンダ」2004年、南アフリカ・イギリス・イタリア合作、DVD
「ジェノサイドの丘」(上下2巻)
フィリップ・ゴーレイヴィッチ著、WAVE出版、各1600円+税
著者は「THE NEW YORKER」等のスタッフライター。


